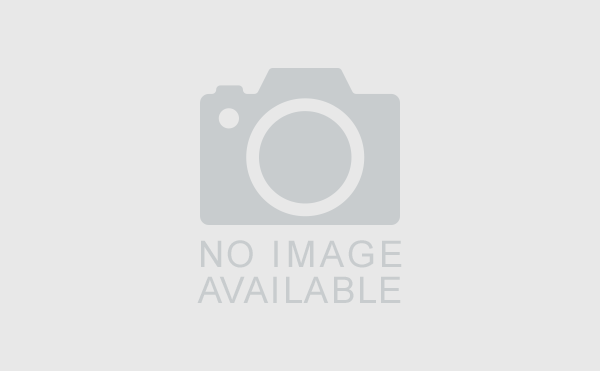2024炭焼き体験された皆さま
炭焼き体験をして、さらに炭のことをたくさん知ろうと思った

昔から夏は炭焼きをしていなかった。
季節的にも夏は農繁期で炭焼きどころではない。実際に焼いていると確かに夏場の樹液の活発な木は炭が軽い。
さらに窯内の流体をおこすための温めは、煙突から出る煙の温度と外気温の温度差で決まるので、夏場は流体を起こさせるのに大変であること。
近年まれな連日猛暑の中、切明畑さんが炭焼き体験に来た。
炭そのものは時々使っていたので知っていたが、身近な燃料としての炭がどのようにして作られているのか知りたくて挑戦されたのだ。
江戸時代、あるいはもっと昔から炭窯で焼かれていた炭が、実は近代石油化学プラントと同じ原理で焼かれていたことに驚いていた。
炭窯内の情報は煙突の煙ですべて分かることも感激していた。
8月5日に窯出しをすると、自分で持ち込んだイチジクの故木も竹も松ぼっくりもきれいな炭になっていた。もちろんカシ材はとても硬い炭だ。
切明畑さんは、これからはもっと炭を生活に取り入れ、炭のことをたくさん知ろうと思っているそうです。
猛暑の中お疲れ様でした。
今まで焼いていた炭とは全く異なる炭に感動

芝山町竹炭サークル「かぐや姫」の内藤さんと、同サークルでも活動している多古町地域おこし協力隊の佐藤さんが炭焼き体験に来ました。
「かぐや姫」では既存の炭窯を使って何度か竹炭を焼いていますが納得出来る炭が焼けなかったとのことで今回の炭焼き体験となったそうです。
今までの認識を改めるため、炭窯は化学プラントであることを説明し窯の中に入れた木や竹を徐々に熱し木や竹を構成している水分や繊維・木ガス・タールなどを窯外へ煙突から揮発させ、炭(炭素とミネラル)を窯内へ固定させる仕組みを説明しました。
また重要なことは窯内に固定された炭に酸素が入ると着火し燃えてしまうので、窯内温度が下がるまで完全密封をすることを学んでいただきました。
7/17㈬に窯入れから焚き込み・炭化管理を体験し、18㈭にネラシで窯内温度を800℃にあげ止め窯を体験しました。
そして窯内が冷めた23㈫窯出しをしました。
今回は杉と竹を炭材にして焼きました。
次々に出てくる炭は今まで焼いていた炭とは全く異なる炭に感動していました。竹炭の金属音には驚いたようです。
杉材は燃料としての炭には少々劣りますが、バーベキューには十分使えます。
多古・芝山周辺では杉林が沢山あり、木材としての利用がほとんどないので、杉炭の活用も今後考えていくと新しい夢を語って下さいました。
さらなるご活躍をご期待申し上げます。
里山の保存には炭焼きが欠かせない

鋸南里山保存会の石崎さんと三浦さんが炭焼き体験に来ました。
石崎さんは里山の保存には炭焼きが欠かせないとの考えから炭窯づくりを見据えての体験です。
三浦さんは鋸南の山奥に移住し米作りをしながら地域活性化に取り組んでいて炭焼きが大きな鍵になると考えている様です。
体験用の炭木は事前に持ち込み、その本気度が感じられました。
6/22、ミーテング後炭木の立て込み。
炭材は雑多な雑木ですが、体験用の炭木としては十分。
予定通りアブリ・焚き込みと進み、17時前には初日が終了しました。
6/23、煙の温度がなかなか上がらず午後からネラシに待機する。
結局ネラシの始まりは19時からとなり、止め窯は22時。お疲れさまでした。
6/30、11時から窯出し。
次々に出てくる炭に感動し体験は終了しました。
今年度中に炭窯を作りたい石崎さんはとても良い体験となったと話し、三浦さんはネラシの窯内は化学の領域から妖艶な世界を垣間見たと話していました。
鋸山南の里に炭焼く煙の立ち昇ることを応援します。
小窯は炭窯の命だ

5月18日、「NPO冨里のホタル」の山崎さんと鈴木さんが中級コースの炭焼き体験に来ました。1月の末に初級コースを体験しさらに習熟を深めようと取り組みました。
今回は前回のレポートに沿って自ら作業を進めました。
窯入れからアブリ・焚き込みと順調に進みましたが、二日目の炭化の進み具合が悪いのです。
煙の温度がなかなか上がらず、ついに夜は半兵衛が引き受け、止め窯が翌朝2時になるという状況でした。
しかも窯内の温度は780℃ほどまでにしか上がらず、窯内はいつもは金色にかがやくのですがどうしたのでしょうか。
しかし窯内は落ち着いた赤色で、しかも紫がかった炎がゆらりゆらりと揺らめいているではありませんか。
煙突からの煙は全くなくなっている。
この窯内状況をどこかで見たと思ったら本窯の止め窯と同じ状況だったのです。
小さな炭窯だけど窯内への空気の流入が少なかったのでしょう。
ゆっくりと炭化した。これは良い炭が出来ると確信しました。
1週間後窯出しをすると確かに良い炭が出てきました。
手にずっしりと重さを感ずる炭です。
なぜそうなったか検証するため最後に小窯を確認すると、煙突を立てるときに落ちてしまったベトが少し落ちているなど小窯の流体が弱くなっていたことが原因かと推察されました。
今回は小窯の清掃確認は毎回おろそかにせず窯入れ前にしっかりすることを学びました。 炭焼きは毎回状況が変わり学ぶことが多いですね。
竹炭にとりつかれて

つくばの池田さんご夫妻が竹炭の窯出しに来ました。炭焼き体験はこれで4回目です。
竹は孟宗竹、昨年12月9日に炭窯近くの竹林で伐採し、割り、節を取り、荒縄で束り5ヶ月風通しの良い屋内で乾燥させた水分を20%ほどに落としたものです。
この竹を5/3に窯入れ焚き込み、5/4にネラシ止め窯をし、12日に窯出しに来ました。
竹は水分を落として焼くと本当にきれいに焼けます。急激な収縮がないためひび割れはほとんどありません。
一緒に入れたヘチマもきれいな炭になっていました。
奥さんは竹炭を使った商品を作りたいとのこと。ぜひ挑戦してほしいものです。
今回は奥様のお母さんもおいでになり窯出しをご覧になりました。きれいに焼けた炭と窯周辺風景の美しさに感動されていました。奥様のお母さんはとてもかわいい元気なおばあちゃんです。とはいえ私とほぼ同年です。これからもお元気で。
大昔から伝わっている炭窯が石油コンビナートと同じ仕組みだったとは

4/23、姉ヶ崎の嶋崎さんが炭焼き体験に来ました。
嶋崎さんは弟子の南田さんと炭木の伐採・運搬・木づくりと事前準備も体験しました。
嶋崎さんの住んでいるところから京葉工業地帯の石油コンビナートも望むことが出来るそうで、炭窯が原油を蒸留させ様々な石油製品を取り出すように炭窯内の原木を温度を高めながら炭以外の物質を次々と揮発させ炭を作ることを知り感動していました。
初日は打ち合わせ後窯入れ、アブリ・焚き込みと順調に体験し終わりました。
24日は、正午からネラシに入り窯温度をあげ、15時に止め窯をしました。
28日は窯も温度が下がり窯出しをしました。炭は奥に行くほど金属音のする硬い炭となり窯内のどの辺の炭が良質なのかも知ることが出来ました。
終了の会ではNo191番の終了証を差し上げました。
杉炭に挑戦

4/8~9日の炭焼き体験、沼津の河西さんグループ4人が来られた。1年前も体験に来られたことがある。
地元お寺の山を整備していて、ここに炭窯を作り拠点としたいとのこと。今回は山に植林されている杉を炭にしてみたいとのことで挑戦された。
杉は堅木の中に数本入れて焼いたことがあるが、通常の時間で焼くことが出来た。
1日目は少々時間がかかったものの、夕方までには煙の温度は80℃に安定し口を小さくして作業を終えた。
2日目は朝8時になっても90℃少し超え、いつもは140℃前後になっているのだが。
結局夜遅くなるので帰っていただき、当方でネラシ、止め窯を行った。終わったのが真夜中になってしまったのだ。
この原因が良く分からない。
14日の窯出しの時に煙道を確認すると煙突を立てる時に落ちたものか煙道下部にベトの固まりが少々落ちていた。
とにかく焚き込みの時の煙に力強さが欠けていたことを思い出した。
今回の状況を踏まえ数か月後に、もう一度炭焼きをしたいとのこと。私も気がかりなのでお願いしたいところだ。
10年後に再度炭焼き体験を

東京の高野さんが炭焼き体験に来ました。
高野さんは丁度10年前に体験されたことがありましたが、他のグループの方と一緒だったことからポイントを十分理解できなかったことと、実家の片付けで火鉢など炭を使う道具が沢山出てきたことから改めて炭焼きの基本をもう一度理解したく来られたそうです。
3月27日に窯入れからアブリ・焚き込みを体験し、28日はネラシと止め窯を体験しました。
高野さんは180cmを超える大男で窯の中に入るのがやっとという感じでしたが、さすが沢登りのベテラン、柔軟な体で難なく炭木を立て込み、次々と作業をこなしていきました。
28日はネラシが最大のイベントでしたが、なぜか窯が言うことを聞かず夕方からネラシをする始末になってしまい帰宅は22時を過ぎたようです。
体験三日目は窯が冷めた4月3日。生憎小雨が降り出す天候になりましたが、弟子のよう子さんが手伝い炭出しを体験しました。
窯出しをした炭は思っていた通りの出来栄えで、感動された様です。
高野さんは施設管理の仕事をされているそうで、理系の人らしくアブリで窯口から煙突口へ流体を起こさせることが大きなポイントであり、窯内の炭木が300℃近くになると炭木自体が発熱し炭化が進んでいくことなど良く理解されました。
帰り間際に「1時間も走れば炭窯に来られるから、炭木の伐採にもきますよ」と有難い助っ人話もしてくださいました。
地域おこし協力隊で炭焼きを

3/4、東京の前田さんご夫婦が炭焼き体験に来ました。
前田さんご夫婦は地域おこし協力隊として4月から金沢市の東原町へ赴任し、炭焼に取り組むとのこと、そのため一通りの炭焼きの流れを学びに来ました。
始めて入った炭窯の中、そして煙に涙しながらの火燃し。
体験するすべてが今までとは全く違う環境のお仕事のため、とても熱心に体験されました。
3/5、ネラシと止め窯。煙の色の変化、窯内炭の黄金の輝き、臭い等々これから日々の生活になるんですね。
3/10、窯が冷めての炭出し。
出てくる炭は奥に行くほど良い炭になっていくことが実感として分かったようです。出した炭の山に感激。
前田さん本当にご苦労様でした。
新天地でのご活躍をお祈りいたします。
放置山林の活用を学ぶ

木更津の鈴木さん、土屋さん、君津の南田さんが炭焼き体験に来ました。
鈴木さんは将来実家の富津市へ戻り山と田畑を活かした生活を展開されるそうで、その一つの柱に炭焼きを計画しているとのこと。
土屋さんは竹が山を登る環境変化を憂え竹灯籠製作に取り組んでいて、さらに作品に幅を持たせるため炭に出来ないかと挑戦されました。
南田さんは当塾の取り組みに感動し、その意志を後世に継ぐため学びたいと参加されました。
三人はとても気が合って体験に取り組み、予定通りに全工程を終了しました。
木が炭になる化学的仕組みが分かり、現在の様に温度計がない時代は煙の色・匂い・煙の流れる形で炭化状況が分かることも学びました。
終了式後の感想として、鈴木さんは先ず地元の長老を尋ね、炭焼きを経験された方からノウハウ等を聞き取ることから始めたいと話されました。
土屋さんは竹を形の良い炭にするときは乾燥状態がカギになることを学んだので次はそれらを踏まえ挑戦したいとのこと。
南田さんは炭焼き技術と土窯半兵衛の功績を後世に伝えるためさらに学びたい。
と、皆さん頼もしい心の思いを披露してくださいました。感激![]()
第二の人生は故郷で炭焼きを

2/10・11日と退職後は郷里の秋田で稲作と山仕事に取り組むという佐倉の鈴木さんとその仲間お二人が炭焼き体験に来た。
天候に恵まれ風は窯口から煙突方向に吹く炭焼き日和り、ミーティングで炭焼き工程のポイントを把握し炭焼きの実体験をされた。
えっ、こんな小さな炭窯で炭が焼けるのとの感想を持ちながら、大きな体を窯の中へ滑り込ませ炭木を立て込む。
体験窯は2日間で窯入れから止め窯までの全工程を体験するために設計した大きさだ。
体験してみると意外に沢山の木が入るのに驚く。最初のポイントは窯内へ密に炭木を立て込むことだ。
第2のポイントは窯内を暖め窯口から煙突へ空気の流れ、流体を起こさせる様に窯口で火を燃やすことだ。
第3は窯内天井の乗せ木が自ら熱を出す(炭化)温度に安定させるまで、火を燃やし続けること。
安定したら窯口を小さくして初日の体験は終了する。
2日目は炭化が進むたびに煙の色が変化し臭いも鼻を衝く匂いになってくる。
最後の煙り浅葱色が薄くなってくると炭を固くするためのネラシを3時間ほど行い止め窯をし作業を終わる。
2/17㈯に佐倉の鈴木さんとその仲間のお二人が体験窯の窯出しに来た。
はやる気持ちを抑えながら窯口の石を開けると白い灰に覆われた炭が見えた。
あれっこんなに少なくなってしまうの![]() との感想。
との感想。
ネラシで空気を送り込み窯内を高温にするためどうしても入り口付近は燃えてしまうのだ。
でも炭を出し始めると、自分で焼いた炭の重さと量、感触に驚く。
窯前にうず高く窯出しされた炭の山に大満足。
今回はカシ・クヌギ・ナラの三種類を焼いたので木の種類による炭の重さの違いを実感できたようだ。
終了会にはレポートを提出していただき体験された方の理解度を確認させていただいた。
鈴木さんには秋田に帰られたら是非とも炭焼きに挑戦していただきたいと思います。
健全な里山を目指して

「富里のホタル」の山崎さん、鈴木さん、井上さんが1/20に炭焼き体験に来ました。
「富里のホタル」の皆さんは北総台地に広がる谷地が活用されずにいることに鑑み、自然環境の復活を目指して活動をしています。
そうした活動の中で谷地に接続する丘陵山林の健全な里山を目指し、炭焼きを取り入れた活動をしたく勉強に来られました。
トラックに現地の炭材、カシ、クヌギ、コナラ等を満載し来窯されるなどとても熱意を感じました。
1日目は、ミーティングの後、炭木の窯入れをし、アブリ、焚き込みと予定通り体験され、2日目は炭を固くするネラシを3時間ほど体験し止め窯、窯内の幽玄な色合いを堪能しました。
1/28は楽しみだった炭の窯出し体験。次から次へときれいに焼けた炭が出てきて体験の成果を改めて感じたようです。
「富里のホタル」フィールドには窯づくりに適した土地と土があるとのことで、今後窯づくりも視野に検討を進めるとのことでした。
「富里のホタル」の皆さん、ご期待申し上げます。