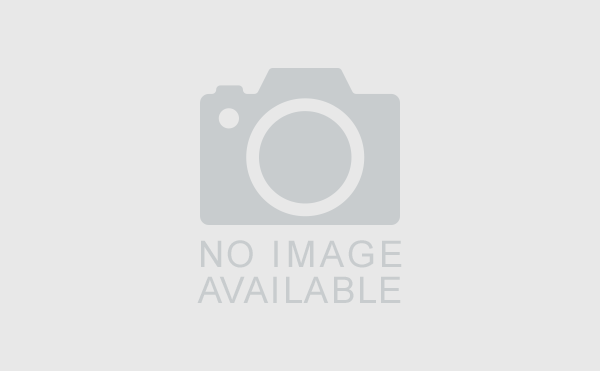炭窯づくり
造成工事(2003.5.8~5.14) 炭窯を造る場所は排水が大事だ。なにしろ炭の原木からは樹液がたくさん流れ出るのだ。現場は元水田なので排水の良い土砂で30cmほど埋立をした。埋立の上に粘土質の土砂で土手を築いた。この土手を堀込んで炭窯を造るのだ。埋立工事は近所の奥村さんにお願いした。写真中央軽トラックの左側が土場だ。土場が完成すると近所の山仕事をしている人などから炭焼に適する樫やクヌギ・楢などの原木がたくさん運び込まれた。有り難いことである。

材料集め(2003.5.18~5.29) 昔から炭窯づくりの石材は砂岩の高宕石が使われていた。高宕石は房総山脈中央の高宕山連山の一角、石射太郎山から大正の初めまで切り出されていた。たまたま私の女房の実家に土台石に使われたものが捨てられずにあったのでいただいた。これは小窯や窯口敷石などに使われた。また側壁の立ち上げには雑石が多量に必要だ。幸い清和県民の森の御協力を得て工事の際発生した石をいただくことが出来た。

地祭り(2003.6.6) 工事を進める上では安全が第一である。安全祈願の地祭りを行った。土窯半兵衛は三経寺に葬られている。半兵衛の遺徳を偲んでの炭焼なので地祭りは三経寺の蓮波住職にお願いした。半兵衛のお墓を代々管理している明石利雄さんにも参加していただいた。三経寺の土窯半兵衛の墓碑には「心縁常性信士、安永元辰年(1772)十二月十一日、相州土肥鍛冶屋村、俗名常盤半兵衛」と記されている。

掘削(2003.6.10) 地祭りを終えて初めて窯づくりの作業に取りかかる。炭窯の大きさは縦2.2m横1.8mのラッキョウ型に高さ1.0mの内空とした。比較的小さな窯である。これは窯の天井が土天井であることや原木の確保、白炭(火取り)も焼いてみたいとの考えからである。土手の上におおよその寸法を描き石積み幅の余裕を見込んで人力での掘削を開始した。

掘削完了(2003.6.10) 土手は粘土質の土砂であり築堤後1ヶ月近く経過したため、表面から30cm程は乾燥が進み人力による掘削は大変だった。しかしそれより下になると丁度良い含水比だったため掘削ははかどった。全部で5立方メートルほど掘削した。明石さんと私の二人で5時間ほどかかった。久しぶりに労働と汗の喜びを実感した。

小窯の設置(2003.6.16) 小窯は排煙施設である。いわゆる煙突を取り付けるところだ。炭窯づくりでは一番留意する。炭を焼くと小窯の方から炭化が進むということだ。小窯の出来不出来が良い炭を焼けるかどうかの分かれ道だ。小窯基部の開口は窯底より幾分低く設置するのだ。そして下部は35cm程の幅で築き上に行くほど狭くなる。いわゆる下部に膨らみを持たせるのだ。これで煙突からの逆風を防ぐことが出来る。

小窯と敷石の完了(2003.6.17) 正面が小窯とその開口部だ。窯底の敷石も完了した。計画では窯底まで石張りを考えてなかったが、幸いに高宕石が十分調達できたので豪華に石張りとした。前面の二本の石柱は窯口である。側壁の石積みも並行作業で進めた。
小窯と敷石の完了(2003.6.17) 正面が小窯とその開口部だ。窯底の敷石も完了した。計画では窯底まで石張りを考えてなかったが、幸いに高宕石が十分調達できたので豪華に石張りとした。前面の二本の石柱は窯口である。側壁の石積みも並行作業で進めた。

ベト塗り(2003.6.19~6.25) 窯の側壁が腰まで仕上がると石積みの目を滑らかにするためにベトを塗る。こねた粘土をたたきつけてなぞっていくのだ。目を詰めると本当に窯らしくなってきた。腰まで仕上がると、次は窯の中に炭木を詰めて窯の内空を確保できるようにして土天井を載せるのだ。現場近くの成戸さんも手伝いに来てくれた。成戸さんは現役の頃は若い衆をたくさん従えて公共工事に携わっていたとのことだ。

原木の立込(1)(2003.7.3) いよいよ土天井を載せるための炭木の立て込みだ。集積してある原木の中から樫を選りすぐって、粗朶にして小窯の周辺から立込む。明石さんは木切れで粗朶そくりの道具をこしらえた。πを逆さにしたようなもので2基つくり、そこに細い木を並べて藁でそくるのだ。炭木の立て込みは窯口に行くにしたがって太いものを立てていく。また窯口近くはほとんど灰になってしまうのであまり価値の無い木でいいのだ。土天井は中央を丸く盛り上げるので周辺の腰より長い炭木を用いる。隙間の無いように一本ずつ丁寧に立て込むのだ。

原木の立込(2)(2003.7.4) 原木の立て込みはほとんど終わりに近づいた。隙間のあるところは後で細い木を詰めていく。小屋組の丸太にちょこんと腰掛けているのは明石さんのお孫さんの偉籍君である。歳はもうすぐ三歳になる。炭窯づくりには必ずついてくる。現場ではみんなのアイドルだ。ジッと見つめられるとおじいちゃんも気が抜けないのだ。

型木載せ(2003.7.5) 土天井を載せるための型木を立て木の上に並べていく。丁度良い天井の丸みにしなくてはいけない。窯の直径が1.8mなので中央の高さは30~40cm程がよいだろう。

切子載せ(2003.7.6~7.8) さらに天井を丸くして均一に粘土を覆うことが出来るように小枝を鉈で切り刻んだ切子で型木の目つぶしをして程良い丸みに仕上げていく。切り子は鉈で刻むため生木がよい。このため近所の森さんの協力を得てエノキの枝をいただいた。切り子を丁寧に並べていくと放物線を描いて芸術的に仕上がった。いよいよ次はテンジョーイ(君津市史民俗編では天井覆いのこととしている)となるのだ。

ぼた餅テスト(2003.7.9) テンジョーイで使う土は粘土だけではひび割れが生ずる。そこで粘土と砂を配合して天井に耐える土をつくらなければならない。写真は粘土と砂の配合を変えて造ったテストピースだ。実際にテンジョーイの時も土のぼた餅を作って天井を覆っていくのだ。左の5個は6月末につくったものでここで使用する粘土と砂では粘土2/3砂1/3が適切と判断した。右のぼた餅は現場配合してつくったテストピースだ。

骨休み1(2003.7.14~15)
一月以上に渡って肉体労働が続いたので、骨休みを取ることとした。骨休みには温泉がいい。そうだ半兵衛さんの生誕地は湯河原町鍛冶屋ではないか。そこで明石さんと二人で半兵衛さんの消息を探る旅に出た。湯河原町役場で伺うと鍛冶屋ではお寺は黄檗宗の瑞応寺だけとのこと、寺に行くと住職のお母さんが11時の鐘を突いていた。半兵衛さんの性は常盤なのでお話しすると鍛冶屋には常盤さんが20軒はあるとのこと。長老の常盤晴夫さん(92)を紹介していただく。晴夫さんの話「半兵衛さんが他国へ行って炭焼を教えたとの話を聞いたことがある。私の所は分家だから歴史は浅い」とのこと。お話の後、息子の清司さんが炭窯や本家の常盤定敏さん(93)宅などに私達を車で案内して下さった。(写真は瑞応寺裏の高台から)

骨休み2(2003.7.14~15) 清司さんの炭窯はミカン畑のずっと上にあった。今は使われてないが、構造も大きさもほとんど私達が造っているものとおなじだ。常盤定敏さんは突然の訪問にもかかわらず私達を快く迎えてくださった。三百年前に建てられた瑞応寺の土地一町歩程を御先祖様が寄付されたといわれるほどの旧家だ。定敏さんは私のノートに土窯の構造図を描いてくれた。この図も私達が造っているものと全くおなじだった。土窯は離れた地でも確実に継承されているのだ。また物置には素金が沢山あって戦争中に供出したとのこと。定敏さんが熱心に語る姿を見ていると半兵衛さんはこのような方ではなかったかと思われてきた。

骨休み3(2003.7.14~15) 鍛冶屋集落の最上流に幕山公園がある。梅林が有名だそうだ。案内して下さった清司さんもこの梅を植えたとのこと。宿泊は公園近くの「まきやま旅館」とした。温泉にゆっくり浸かり海鮮料理とお酒をたくさん御馳走になった。今までの疲れが一気に回復していくようだ。翌朝常盤清司さんが旅館を訪ねてきてくださった。昨夜、晴夫さんから新しいお話を得たという。また吉浜には豪商の常盤さんが居たことなどお伺いしながら再び車で湯河原図書館まで案内していただいた。かねてから連絡をさせていただいた中村さんは不在だったが、代わりの方が郷土の資料を探して下さった。一泊二日の小さな旅の印象は一言で言えば清司さんをはじめ町民の方々の親切にふれることができたことである。半兵衛さんもきっとこうした親切な方であったに違いない。

テンジョーイ1(2003.7.19) いよいよ炭窯づくりでも特に難しいテンジョーイとなった。テンジョーイとは君津市史民俗編によれば天井覆いのこととある。またこの日は作業の性質からたくさんの人手を要する。粘土と砂を配合し練る人、粘土を一定の大きさにぼた餅のように丸める人、このぼた餅粘土を窯の天井に並べていく人などである。昔からテンジョーイにはぼた餅を造りお祝いをしたそうだ。そこで今日のテンジョーイには三経寺の蓮波住職をはじめ写経会の皆さんや御近所の皆さんなどをお願いしてワイワイと楽しく作業をすることとした

テンジョーイ2(2003.7.19) 作業は切り子の上に筵を覆うことから始まる。材料は先のテストピースの結果から粘土2対砂1の配合とした。材料の練り合わせは小型耕耘機を活用した。昔は鍬や足で練ったという。ジョーロの水で含水比を整えながら練る。練った材料はボールに入れ一定の大きさにして手で丸める。赤ちゃんの頭ほどの大きさである。これを一つずつ窯の腰の上から鉢巻きをするように並べていくのだ。

テンジョーイ3(2003.7.19) 粘土ぼた餅を並べているのは明石さんだ。慎重に一個ずつ並べていく。粘土ぼた餅の重さを量ってみると一個当たり平均3.7kgあった。しかし品質管理が勘によるものなのでバラツキが多い。大きさや重さががマチマチになる。練り合わせた粘土は時間が過ぎるごとに乾燥が進んでしまうのだ。それでも何とか手際よく天井を覆っていくことが出来た。

テンジョーイ4(2003.7.19) テンジョーイも頂部に近づいてきた。時々竹串で造った厚さ計測用のバカ棒で厚さを確認する。ほぼ15cm程の厚さは確保できた。しかし次の作業では天井を叩きながら乾燥させるため大分薄くなるのだ。

テンジョーイ5(2003.7.19) テンジョーイが完成したところで記念撮影。初めての仕事だったけれどみなさん満足した様子。結局3.7kgの粘土ぼた餅244個で天井を覆うことが出来た。総重量は900kgになる。お相撲さん6人分の重量だ。この後、火入れ式を行った。窯の中の詰め木には火がつかないように少し燃やしてみる。煙突からほのかに白い煙が立ち上った。ヤッター小窯は十分機能したではないか。明石さんの考えていたとおりに作業は進んだ。

テンジョーイ6(2003.7.19) テンジョーイお祝いには女性も参加いただいた。朝早くから祝宴用の料理づくりに取り組んでいただいたのだ。祝宴の場はは炭窯を見下ろす高台の休憩所。手づくりの料理に参加者全員が舌鼓を打った。とくに現地で焼いた野趣あふれる鳥手羽の炭火焼きは好評だった。

天井の乾燥1(2003.7.20) 天井の乾燥は根気のいる仕事だ。いきなり窯の中の詰め木を燃やすことは出来ない。天井が十分乾燥してからでないと落ちてしまうのだ。そこで窯を暖めながら、ただひたすらに木片で叩くのだ。叩いているうちに中の水分が表面に滲み出てきて乾燥が進む。しかしこれが難しい。粘土は柔らかくなると下の方に下がってしまうのだ。だから下から上に叩き上げるようにしないと頂部が薄くなる可能性がある。また粘土ぼた餅すべてが一定の含水比ではないので油断をすると水分の多いところが流動してしまうのだ。その日の作業を終えると濡れた筵で天井を覆い養生をする。根気のいる仕事が何日続くのだろうか。

天井の乾燥2(2003.7.25) テンジョーイが終わってから、ただひたすら土天井を叩き続けて一週間になった。叩く道具は、明石さんが生の栗の木で造った。毎日使っていたので握りの部分が光り艶が出てきた。窯口からは乾燥させるための火をチロチロと燃やし続けた。昨日までは煙突から水蒸気が白く立ち昇っていたのに、今朝はほとんど出ていなかった。室内が乾燥してきた証拠である。

天井の乾燥3(2003.7.25) テンジョーイが終わって3日目から、炭小屋前後の柱と天井を見通して水糸を張り、天井の下がり具合を測定した。毎日4mmずつ下がり、今日までに12mm下がった。天井が完全に乾燥すれば下がりはなくなるのだろうか。天井は窯口の方から乾燥して白くなってきた。ひび割れが心配なので急激に乾燥しないようさらに留意していかなければならない。

焚き込み(1)(2003.7.28) テンジョーイの次の日からただひたすら土天井を叩き続けた。その間、乾燥のための火を燃やし続けたので窯の中はカラカラに乾燥してきたようだ。昨日は乾燥のために燃やしている火が三度も炭材に燃え移る緊急事態が発生したのだ。加えて天井を叩く音も金属音になったので今日は焚き込みをすることにした。午前9時に明石さんが点火した。

焚き込み(2)(2003.7.28) 点火後、煙突の煙の温度は40℃から70℃へと順調に推移していたが、突然煙突からの煙が途絶えて窯口へ噴出してきたではないか。バックファイヤーだ。炭材が乾燥していたので一気に火が点いてしまったのだ。それからしばらく悪戦苦闘。窯口を小さくして段ボールの切れ端で扇いで風を送り込む。

焚き込み(3)(2003.7.28) 窯の上では木曽野建築所の二人が杉皮屋根の取付作業をしている。テンジョーイ以降は天井叩き作業に支障が無いようにシートで覆っていたが、大雨が近づいている予報もあることから屋根の取付作業をしていただいた。煙に燻されての作業は大変だった。

焚き込み(4)(2003.7.28) バックファイヤーとの悪戦苦闘すること30分、いわゆる窯が怒ったのだ。窯の口を小さくして風を送り込んでなだめた結果煙突から順調に煙が出るようになった。煙の温度も83℃に上昇し窯がスヤスヤと静かになった。これから30時間順調に炭化が進んだのだ。

焚き込み(5)(2003.7.28) 夏休みに入ってから近所の小学校一年生のお嬢さん達が時々遊びにやってくる。炭窯が珍しいのだ。「これが炭を焼く窯だ。ほら白い煙が出ているだろう。」と説明すると。「♪♪炭焼くけむーりに、清和をしのーび。」と歌う。ナ、ナント地元、秋元小学校校歌の一節ではないか。確か私の在学中にこの校歌が出来た。その当時は炭焼く煙はどこでも見られた。しかし炭の需要が少なくなるとともに、学区内では炭焼く煙は絶えて久しいのだ。ムムッ早速コウカがあったのだ、などとシャレてみた。

木酢液の採取(2003.7.28) 木酢液は炭焼の重要な副産物だ。しかしこれに注目されたのはごく最近のことである。もちろん半兵衛さんのころは採取することはなかったであろう。木酢液は消毒・植物の成長促進・土壌改良・薬用など多用途である。しかし今回は窯づくりが目的だったため木酢液採取施設を準備してなかった。そこで急遽トタン板を丸め煙突の上に設置した。これが意外にも効果を発揮し、最終的には20㍑ほどの原液を採取することが出来たのだ。その後木酢液採取施設は錆びないようステンレス製に作り替えた。

炭化(1)(2003.7.29) 窯はすっかり落ち着いてスヤスヤと炭化が進んでいる。煙の温度は83℃をずっと保っている。炭小屋の前では子供達が遊んでいる。明石さんはすでに次の窯入れのための炭木づくりに余念がない。日中安定していた煙の温度が夕方には95℃に上昇した。土天井の上には高温のため陽炎が立ちはじめたではないか。初窯は天井を乾燥させるため窯内を十分乾燥させたから炭化が早まるかもしれない。今夜は眠れないぞ!

炭化(2)(2003.7.29) 夜の9時に確認。一時的に雨が降ったせいもあろうが煙が随分と多い。煙の温度は依然として95℃を保っている。「メーワカレが近づいた」と明石さんがいった。
30日午前1時確認。ちょうど大雨となった。煙の温度を測ると90℃と下がっているではないか。なぜだ?確認すると、なんと急遽つくった木酢液採取用トタン板の溝を雨水が伝わってポタポタと煙突の中に入っているではないか。しかし早く発見できて良かった。木酢液採取用トタン板を取り外すと温度はすぐに上昇をはじめ110℃になった。83℃が30時間続き確実に炭化が進んだのだ。窯内の情報は煙しかないのだ。

炭化(3)(H15.7.30)
朝5時、雨はあがる。窯の煙が大きく立ち上っている。いくぶん黄色みを帯びてきた。きわだ色だ。風は無く穏やかだ。煙の温度は143℃だ。炭化は確実に進んでいる。今日の昼過ぎには止め窯になるのだろうか。
午前7時40分、煙の温度は174℃浅葱色になってきた。(写真)背後の山の朝霧と比べるとよく分かる。
午前9時、205℃、午前11時、241℃となる。煙は浅葱色から透明に近くなる。そろそろ精錬に入らなければならない頃だが明石さんはほかの仕事でいない。私には次の行動の判断が出来ず、ただ煙と温度計を見つめるだけだった。

止め窯(2003.7.30) 明石さんが12時20分にやってきた。安堵。煙の色を確認し小穴から窯内も確認し、ねらし(精錬)に入った。窯口の下の部分を開けて空気を入れガスを除くのだ。小穴から窯内をのぞくと、赤い炭材に琥珀色の炎が妖しくまといついている。この色はどこかで見たことがあるぞと考えたら、新日鐵君津製鉄所工場見学で見たのとおなじ感じがした。窯内の天井も真っ赤だ。粘土ぼた餅が亀甲状を描いている。ちょうど石積み天井のようだ。写真に撮ることが出来ず残念。煙突からの煙がほとんどなくなったので午後3時に止め窯にした。明石さんが窯口を塞ぎ私が煙道を塞いだ。

土天井クラック調査(2003.8.4) 止め窯の間に土天井のクラック発生状況を調べた。クラックは9箇所で発生していたが、何れも縦クラックなので窯に悪影響を及ぼすものではなかった。長いものでは35cm、短いものは5cm程である。クラック総延長は167cm、土天井の面積は4.33㎡である。したがってクラック率は38.5cm/㎡となる。この数値が妥当かどうかは土天井に関する過去のデータがないので判断できない。いずれにせよ止め窯でも天井が落ちることがなかったので容認できる範囲なのだろう。

炭出し1(2003.8.7) 今年は梅雨が長かったので8月7日は久しぶりに太陽がギラつく一日となった。8時30分初窯の炭出しを開始した。明石さんが窯口の石を取り除くと薄暗い窯内が見渡せた。止め窯から一週間も過ぎていたので窯内の火照りはほとんどなく外気とおなじ28℃だった。昔の炭出しは次から次に炭を焼くため窯内が熱いうちに作業に入る。したがって熱さよけに綿入れを着たという。今朝もお婆ちゃんが心配して綿入れを二枚用意してくれた。しかし使わずにすんだ。

炭出し2(2003.8.7) 窯内に入ると、窯づくりのときギッシリ詰めてあった炭木が小窯のほうに倒れて随分少なくなっていた。テンジョーイの時の筵が炭化して炭の上に覆いかぶさっている。原木の種類によっても違いがあるのだろうが一体どの程度に小さくなってしまうのだろうか。

炭出し3(2003.8.7) はじめに明石さんが窯の中に入り炭出しの作業をする。炭は葦簀で作った搬出用モッコに載せて窯の外に出す。昔は炭俵で作ったそうだが、今は炭俵がないのだ。炭は窯口に近いところは燃えてしまっていたりスボタがあったりして焼け方が悪い。これは初めから予想できたので炭としては価値の低い雑木を立てておいた。小窯に近づくにしたがって良く焼けていた。この部分にはカシやナラなどの良質炭材を立て並べた。出した炭は後で製品の区分がしやすいように順序よく並べた。

炭出し4(2003.8.7) 出した炭と窯をバックに記念撮影。心配された初窯は天井が落ちることもなく安堵した。炭材を寄付してくださった方々、テンジョーイで労力をいただいた方々、ご近所の方々、湯河原町の皆様、そして南無土窯半兵衛様、皆様方に心から感謝を申し上げます。

炭出し5(2003.8.7) 炭を出し終わってから窯内を確認した。土天井は粘土ボタ餅が亀甲状の目地を浮かび上がらせてきれいにドームとなっていた。巨大な素焼きの陶器が出来上がったのだ。クラックはあったが心配するほどではないようだ。クラックは窯口に近い方に発生が多かった。これは乾燥のために火を燃やし続けたため、叩きが十分でないうちに乾燥してしまったためと考えられる。側壁(腰)の部分はベトの剥がれが少しはあるが構造の欠陥となることはなかった。土窯は無事完成を見た。今後は水に十分注意すれば長く使用に耐えてくれるだろう。

炭出し6(2003.8.7) 炭出しが終わると二窯目の炭材の窯入れを行った。昔から土窯は窯内の湿りを恐れるため、すぐに次の火入れ準備をしたという。幸いに炭材を豊富にいただいてあったので木拵えは出来ており、引き続き炭木の詰め込み作業を行った。

炭出し7(2003.8.7) 窯から出した炭がうずたかく積まれた。細めのカシは良く焼けていた。二窯目に火入れをして、窯の前では炭を箱詰めにするための切断作業だ。おなじ寸法で切断できるように切断台に載せ鋸で挽く。炭はアルカリが強いため手の皮膚が薄くなってしまう。私は軍手をして作業をしたが、軍手の先が破れてくるのだ。

炭出し8(2003.8.7) 炭は17cmに切断した。これは10号の段ボール箱に詰めるための寸法である。段ボール箱にはキッチリ3kgの炭が入った。箱詰め用の炭はほとんどがカシでナラが少しあった。初窯の成果は、3kg入り段ボール箱が50箱で150kg、雑炭が米袋9袋で90kg、合わせて240kgあった。昔は炭俵1俵が4貫目(15kg)だったので16俵出たことになる。ほぼ考えていたとおりの成果だった。

炭出し9(2003.8.7) 炭を詰めた段ボール箱には「初窯半兵衛炭」と「燃料用木炭使用上のご注意」を添付した。初窯の炭は、炭焼に御世話になった方々へ御礼の御挨拶代わりに贈呈させていただいた。
初窯の反省点は、煉らし(精煉)が急激だったため炭木の下の方に亀裂が生じてしまったこと、炭材が春先に伐採されたので炭のしまりが少し甘くなったことなどである。しかし製品としては何ら遜色はないものであることを御報告する。