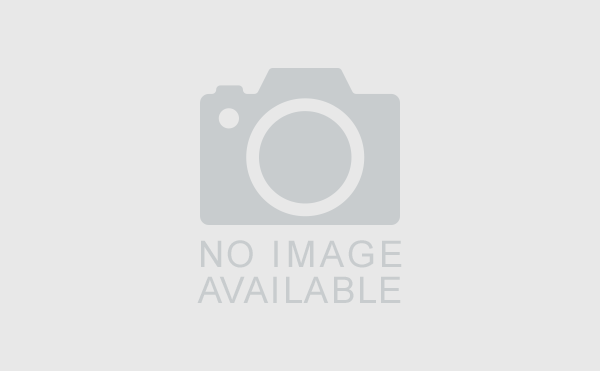土窯半兵衛について
今から250年ほど前の宝暦14年に常盤半兵衛という人が相州鍛冶屋村からやって来て君津の山村に土窯を築いて炭を焼く方法を教えてくれました。カシなどの硬い木に恵まれたこの地からたくさんの炭が焼かれ、小糸川の川舟で河口の河岸に運ばれ、さらに江戸へ運ばれました。質の良い炭は「上総木炭」と呼ばれ、江戸で大量に使われたので、この地は経済的に大変豊かになりました。
郷土の恩人常盤半兵衛は土窯半兵衛と親しく呼ばれ、安永元年12月11日に亡くなりました。市宿三経寺にお墓と顕彰碑があります。


今では燃料としての炭の利用がほとんどないため、山へ木を伐りに行くことがなくなりました。木を伐らなくなった山は大変荒れていて、山崩れが起こる心配があります。また、猿やイノシシなどの動物も山に住みにくくなり里へ出てきて農作物を食べ荒らしています。
半兵衛炭焼塾では、常盤半兵衛の遺徳を偲び炭焼技術と炭文化を後世に伝えるために土窯をつくり炭を焼くとともに炭焼き技術の指導と資料の展示を行っています。